![]() 2015.10.16
2015.10.16
アーツマネジメント連続講座 講座⑧『芸術活動と法務―契約と著作権、公演をめぐる法律』6月30日レポート
 講座8「芸術活動と法務―契約と著作権、公演をめぐる法律」の2日目は、骨董通り法律事務所 弁護士で島根大学法科大学院教授の桑野雄一郎先生を講師に迎えました。昨日のの増山さんのお話にもつながる「著作権」、そして舞台芸術をめぐる「法律」「契約」についてお話しいただきました。
講座8「芸術活動と法務―契約と著作権、公演をめぐる法律」の2日目は、骨董通り法律事務所 弁護士で島根大学法科大学院教授の桑野雄一郎先生を講師に迎えました。昨日のの増山さんのお話にもつながる「著作権」、そして舞台芸術をめぐる「法律」「契約」についてお話しいただきました。
まずは、「舞台芸術と法律・契約」についてのお話から。
舞台芸術の公演に際しては、実際に契約書(書面)を取り交わしているか否かに関わらず、さまざまなな契約行為が行われています。いまだに口約束が横行しているもの事実ですが、書面上で契約を交わしていなくても、口約束でも契約は成立してしまいます。問題が起こらなければいいのですが、ひとたび問題が発生したときには、責任の所在をめぐって言った言わないの大問題に発展してしまいます。
例えば、ひとつの公演については、主催者、出演者、会場と、それぞれに以下のような契約関係が発生し得るでしょうか。
①主催者-施 設 : 会場の使用に関する契約
②主催者-出演者 : 公演の実施に関する契約
③主催者-来場者 : 公演の鑑賞に関する契約
④主催者/出演者-作品の権利者 : 権利処理に関する契約
④は、作品の主催者や出演者が、上演する作品の権利に関して負うべき責任に対する契約です。例えば過去には日本でも、有名な振付家による作品をある外国人ダンサーが振付家本人の許可なく踊ったことによって訴訟問題に発展した例があります。この裁判では、公演を主催したプロモーター(ダンサーの招聘元)にも、著作権侵害の責任があるという判決が下されました。(オリジナリティが認められる場合は「振付」も著作物なのです!)
劇場・音楽堂等の自主事業のように施設=主催者となる場合は、施設(主催者)が上演作品の権利に関する責任を負うことになります。
芸術団体が制作したものを買い取って劇場の自主事業とする、いわゆる買取公演の場合も同様です。
 契約書は、起こりうるトラブルをできるだけ回避し、責任の所在や処置を明らかにするために取り交わすものですが、それでもアクシデントが発生することはあります。
契約書は、起こりうるトラブルをできるだけ回避し、責任の所在や処置を明らかにするために取り交わすものですが、それでもアクシデントが発生することはあります。
そのひとつが、「契約違反」です。交わした契約と異なる事態になれば、当然問題に発展します。
何らかの事情で公演が中止になった場合も同様です。公演の中止は天災などの不可抗力の場合と、そうでない場合に分けられます。あらゆる事態を想定して、アクシデントが生じた際には誰が判断し、誰が責任を負うのかを契約書上で明確にしておく必要があります。近年は、SARSや鳥インフルエンザなど感染症・伝染病によるリスクで実際に公演やイベントが中止になった事例もありますが、これを不可抗力とみなすか否かについてはいまだ議論の分かれるところです。
また、公演が延期になったり、演目や出演者が変更になることもしばしばあります。この場合は、主催者と出演者、会場の三者だけでなく、主催者と来場者(観客)との契約関係にも大きく影響します。出演者が変更になった時に、チケット料金の払い戻しに応じるか、応じないかも、チケット購入時に交わされる重要な契約事項のひとつです。
また、契約関係とは別に、公演の運営に伴うアクシデントによって発生する法律問題もあります。
例えば、会場内での事故。出演者がケガをした場合、また来場者(観客)がケガをした場合、誰がどのような責任を負うかは、事故の状況によって異なるでしょう。
このほか、会場内での無許可の撮影や録音、違法グッズの販売などは、著作権や肖像権、パブリシティ権の侵害に相当する法律問題です。ダフ屋に至っては、迷惑防止条例違反という立派な犯罪です。
公演の主催者は、契約上のトラブル以外に、こういった諸々の法律問題にも対応していかなくてはなりません。
桑野先生によると、「契約書の締結」と、「契約の成立」は、別問題だそうです。冒頭でも触れたとおり、「口約束」でも録音や記録が残っていれば契約は成立しますし、メールのやり取りを根拠として契約成立とするケースもあります。契約書を交わしていないから契約は成立していないと思っていると、大きなトラブルに発展しかねません。
契約書を作る最大の目的は、契約(合意)内容を相互に確認し、それを証拠に残すことです。したがって、契約書にサインしたということは、その内容を理解し、納得したとみなされます。契約書を合意内容と異なる文言にしないのは言うまでもありませんが、内容がよくわからないものに対して安易にサインはしないということも重要です。
また、取り交わされる書類の表題が「契約書」ではなく、「覚書」や「協定書」となっているものも多々ありますが、法律上はどれも契約書であることに変わりありません。
また、普段、何気なく使っている「及び/並びに」や、「又は/若しくは」という表現には、実は法律上は明確な違いがあるのです!契約書において「○○と△△、そして××」のような「集合」を表現する場合は、よ~く注意する必要があります。
そのほか、契約書上の各条項において注意すべき点も、具体例を見ながら学びました。
 続いての話題は、著作権について。
続いての話題は、著作権について。
まずは著作権法の全体像について概観しで、昨日の講座でも出てきた「著作権の権利者」や「著作物」についての具体的な範囲をより明確に説明くださいました。
著作権は、著作物を創作した者に帰属するのが原則です。しかし、作品の買い上げや委嘱作品などの場合、買った側・委嘱した側に著作権が委譲していると勘違いし、自由に使ってしまった結果、本来の権利者(著作者)とのトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
桑野先生はこうした問題について、大工さんに建築を依頼して作ってもらった家(=著作物)の著作権は誰に帰属するのか、という例え話で解説してくださいました。家に住むのは依頼者(施主)の権利ですが、建築物の著作権は設計をした人に帰属するため、設計者に無断で同じ家をもう一つ建てることはできません。
また、一つの作品の著作者が、常に一人であるとは限りません。楽曲のように作詞と作曲が別人の場合もあれば、演劇でも複数の作家が共同で書き進める脚本もあります。映画ともなると、プロデューサー、監督、撮影と、著作に直接かかわる人が大勢いるため権利関係もそれだけ複雑です。こうした共同著作物や、著作物を翻訳・編曲・脚色した「二次著作物」などを使用する際は、権利関係の確認に注意が必要です。
これまで何度も「著作権」という言葉が登場しましたが、実は「著作権」という名称の法的権利はありません。
複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳・翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利…といった膨大な数の権利の総称が「著作権」なのです。
権利者に無断で著作物を使用するということは、これらの権利に何らかの形でふれること、あるいは侵害することになり、窃盗に相当する犯罪を犯すことになるという認識を持たなくてはなりません。
これは、芸術活動に係るすべての皆さん、そして芸術を楽しむすべての皆さんに、今一度考えていただきたい問題です。
![GEIDANKYO 公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会[芸団協]](https://www.geidankyo.or.jp/okinawa/wp/wp-content/themes/okinawa/img/okinawa/logo_geidankyo.png)
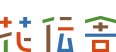



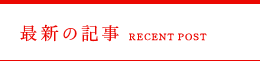

 2018年06月(1)
2018年06月(1)![GEIDANKYO 公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会[芸団協]](https://www.geidankyo.or.jp/okinawa/wp/wp-content/themes/okinawa/img/common/txt-fotter.gif)